情報通信技術教育者合同会議プログラム
- 14:45-15:15
- 基調講演1「人づくりの現場から」
IT教育における課題を大学、および専門学校の観点から提示し、共通の課題とそうでないものを整理し、大学と専門学校間を含めた学校間での課題の共有を行う。更に、1校だけで解決できない課題について、産業界、資格関連団体への協力依頼、初等・中等教育への希望する内容を提示し、課題解決のために学外の団体との連携強化を考える場とする。

講演者 木下稔雅氏
日本電子専門学校 産学連携教育 企画科長
プレゼンテーション資料 [197KB] ![]()
1981年3月に明治大学 工学研究科を修了。同年4月に日本電気株式会社へ入社。ビジネス向け交換機システムの基本開発,および,ネットワークSEに従事。1991年3月より現職。ネットワークおよびセキュリティ関連学科の設立と運営等を行う。現在,電気工学科の科長を兼務。
![]()

講演者 三田淳司氏
長崎総合科学大学 情報学部 経営情報学科専任講師
プレゼンテーション資料 [352KB] ![]()
東京生まれ。学部、大学院では「船舶工学」を学ぶ。工学修士。船や海洋浮体構造物の水槽実験が専門。実験のための計測技術からコンピュータプログラム、電気回路などを学んでいる内にコンピュータネットワークが登場し、そちらが面白くなってしまった。お酒と車が好きだったが、肝臓を壊して禁酒中。今はヤフーオークションで落札した「14年落ち、7万円のクラウン」を整備して遊んでいる。
![]()

モデレータ 江崎浩氏
ICT教育推進協議会会長 東京大学大学院情報理工学研究科教授
ICT教育推進協議会会長。WIDEプロジェクト代表。 MPLS-JAPAN代表、IPv6普及・高度化推進協議会専務理事、JPNIC副理事長、ISOC(Internet Society)名誉理事(Emeritus Board of Trustee)。日本データセンター協会 理事/運営委員会委員長。工学博士(東京大学)。
| 1987年 | 九州大学工学部電子工学科修士課程了 |
| 同年 | 株式会社東芝入社 総合研究所にてATMネットワーク制御技術の研究に従事 |
| 1990年 | 米国ニュージャージー州ベルコア社(2年間) |
| 1994年 | 米国ニューヨーク市コロンビア大学CTR (Center for Telecommunications Research)にて客員研究員。高速ネットワークアーキテクチャの研究に従事(2年間) |
| 同年 | ラベルスイッチ技術のもととなるセルスイッチルータ技術をIETFに提案し、その後、セルスイッチルータの研究・開発・マーケティングに従事。IETFのMPLS分科会、IPv6分科会では、積極的に標準化活動に貢献している。 |
| 1998年 | 東京大学大型計算機センター助教授 |
| 2001年 | 東京大学情報理工学系研究科助教授 |
| 2005年 | 現職(東京大学情報理工学系研究科教授) |
- 15:15-15:45
- 基調講演2「産業界から見た、これからのICT技術者への期待」
インターネットの普及拡大に伴い、ICT産業はクラウドコンピューティングやユビキタスネットワークを中心とする新たな時代に入った。情報通信技術は今後も、様々な経済活動を支えるうえで必要不可欠なインフラとして、重要な役割を期待されているが、その一方で、わが国のICT産業は厳しいグローバルな競争環境にさらされており、大きな転換点を迎えつつある。日本が国際競争に勝ち抜いてゆくうえで、企業としてこれからのICT技術者に期待する資質について、幅広い視点から提言する。

講演者 矢野薫氏
日本電気株式会社 代表取締役会長
プレゼンテーション資料 [2.9MB] ![]()
矢野薫は2010年4月、代表取締役 会長に就任し、当社の事業運営の基本的重要事項を総括しています。
会長就任以前には、社長としてIT・ネットワーク融合領域の事業強化を進めるとともに、NECグループの方向づけに取り組んできました。さらに、今後のNECグループが目指す姿(ビジョン)と、その実現のために大切にすべき価値観(バリュー)を策定し「NEC Way」を体系化しました。このビジョン・バリューとNEC Wayに基づき、NECグループが「One NEC」としてお客さまに貢献し、成長・発展していくための様々な改革を実行してきました。
矢野は1966年の入社以来、約20年にわたって通信機器の開発に従事した後、NECアメリカ社に出向し、北米における通信機器の開発・販売を担当しました。その後、国内・海外において主にネットワーク事業部門の要職を歴任し、インターネット化/IP化による急激な環境変化に直面した同事業の再構築を指揮しました。また、研究開発部門担当としてNECグループの技術開発を牽引してきました。
キャリアを通じて、先進的な技術によるイノベーション(革新)に力を注ぐと同時に、内外の通信事業者、官公庁、民間企業等、幅広いお客様との信頼関係を築いてきました。また、大学院留学を含め3度にわたる海外駐在を経験し、国際的な視野を持つことでも知られています。
- 16:00-17:30
- パネルディスカッション「ICT教育Square」
産業構造、社会問題、国際化対応など、ICT教育が取り巻くあらゆる問題について、会場の参加者と対話しながら、今後への課題とICTEPCの役割、提言などについて議論する。
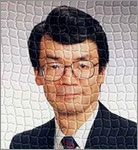
モデレータ 吉田眞氏
ICT教育推進協議会運営委員 東京大学 名誉教授
プレゼンテーション資料 [909KB] ![]()
元NTT、NTT-AT役員、東京大学大学院 工学系研究科教授
TMForum Distinguished Fellow
![]()

パネリスト 山下義人氏
ゾーホージャパン株式会社 代表取締役社長
プレゼンテーション資料 [516KB] ![]()
| 1980年3月 | 早稲田大学理工学部電気工学科卒業 |
| 1980年4月 | 日本ユニバック(現日本ユニシス)に入社通信ソフトウェアの開発に従事 情報処理学会(ISO SC6)の標準化委員を務める |
| 1989年4月 | 日本鋼管株式会社(現JFE)に入社 新規IT事業の立上げに参画 1990年4月より1993年4月まで、米国NetLabs社に駐在 CMIP、SNMPなどのシステム開発に従事 OSI NM/Forum(元、TMF)にNKK代表で参画 2001年3月末に退社 |
| 2001年4月 | 米国AdventNet社に勤務 米国AdventNet社VP |
| 2001年9月 | 米国AdventNet社の日本法人を設立 同代表取締役に就任 |
| 2009年7月 | 社名をゾーホージャパン株式会社に変更 現在に至る |
![]()

パネリスト 三田淳司氏
長崎総合科学大学 情報学部 経営情報学科専任講師
東京生まれ。学部、大学院では「船舶工学」を学ぶ。工学修士。船や海洋浮体構造物の水槽実験が専門。実験のための計測技術からコンピュータプログラム、電気回路などを学んでいる内にコンピュータネットワークが登場し、そちらが面白くなってしまった。お酒と車が好きだったが、肝臓を壊して禁酒中。今はヤフーオークションで落札した「14年落ち、7万円のクラウン」を整備して遊んでいる。
![]()
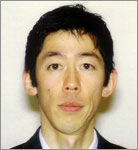
パネリスト 長部謙司氏
シスコシステムズ合同会社 シスコネットワーキング アカデミープログラム マネージャー
2008年2月Cisco Systems合同会社に入社、Cisco Networking Academyを担当する他、Stanford大学との日本の起業、起業家を研究するプロジェクトも担当する。 また、いくつかのグローバル人材育成プログラムにも従事する。
- 13:00-14:00
- 学生向けプレセッション「ボーダレスネットワーク時代が求める人材とキャリアパス」
世界中で事業を展開している企業が、いまどのような人材を必要としているのか、シスコ システムズを例に紹介する。
また、シスコ システムズをはじめとする、ICT企業への就職を希望する学生向けに、学生の内に何を準備するべきなのか、また就職後にどのようにキャリアパスを構築してゆくことが可能なのかを紹介することで、学生による目標設定と就職活動を支援する。
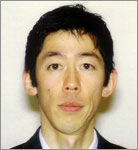
講師 長部謙司氏
シスコシステムズ合同会社 シスコネットワーキング アカデミープログラム マネージャー
2008年2月Cisco Systems合同会社に入社、Cisco Networking Academyを担当する他、Stanford大学との日本の起業、起業家を研究するプロジェクトも担当する。 また、いくつかのグローバル人材育成プログラムにも従事する。
![]()